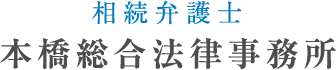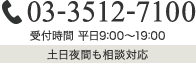![]()
遺言の有効確認訴訟が信義則に反するとはいえないとされた事例(最高裁令和3年4月16日判決)
弁護士
本橋 美智子
![]()
-
1 本件判例の事案
本件判例の事案はかなり複雑なので、ここではできるだけ簡略化して説明します。
母は、平成24年に死亡し、相続人は姉と弟の二人でした。
母は、財産全部を弟に相続させる内容の自筆証書遺言(本件遺言)を残していました。
ところが、姉は母の遺産を法定相続分(2分の1)により相続したと主張して、弟に対し、母の生前になされた売買を原因とする母から弟への不動産移転登記の抹消登記等を求める訴訟(前訴訟)を提起しました。
前訴訟では、弟は本件遺言の有効性について積極的には主張せず、本件遺言の有効性についての判断はされず、姉が遺産について相続分を有する ことについては争いがないものとされ、姉の請求が認められました。 -
2 本判決の内容
そこで、弟は姉に対して、本件遺言が有効であることの確認を求める訴訟(本訴訟)を提起したのです。
本訴訟の一審、控訴審では、姉が母の遺産について相続分を有することで前訴訟が決着しているので、本訴訟の提起は信義則に反するとして訴えが却下されました。
しかし、最高裁は、前訴では本件遺言の有効性が判断されることはなかった、本件遺言の有効性は母の遺産をめぐる法律関係全体に関わるものであるのに対し、前訴訟は母の遺産の一部が問題とされたにすぎず、実現される利益を異にする等の理由から、姉が母の遺産について前訴訟で決着し、今後本件遺言が有効であると主張されることはないであろうと信頼したとしても、この信頼は合理的なものではなく、本訴訟の提起が信義則に反するとはいえないと判断したのです。 -
3 本判決の意義
本最高裁判決は、相続事件についての訴訟提起が信義則違反となるかどうかについての判断基準を示したものとして意義があります。
被相続人が遺言を残していて、その遺言の効力について相続人間で争いがある場合には、まず遺言の有効確認または無効確認訴訟を提起して、その訴訟で遺言の効力の有無を確定しておく必要があります。
それをしないで、徒に遺産分割調停や、相続を前提とした訴訟を先にしてしまうと、後日その調停や訴訟が無駄になってしまう可能性があるのです。