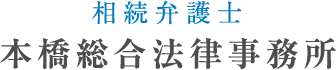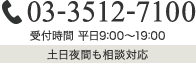![]()
介護による寄与分が一部認められた事例 (東京高裁令和5年11月28日決定)
弁護士
本橋 美智子
![]()
-
第1 事案の概要
被相続人(昭和12年生、令和3年死亡)の長男であるXが、長女であるYに対し、遺産分割の申立てをした。
Yは、Xに対し、相続開始直前まで7年以上にわたり被相続人と同居して介護したことによる特別の寄与を主張して、Yの寄与分を定める処分の申立てをした。
なお、被相続人は、死亡時まで介護認定は受けていなかった。 -
第2
原審の宇都宮家裁大田原支部(令和5年3月3日審判)は、「寄与分が認められるためには、相続人の寄与行為が「特別の寄与」(身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献)に当たり、その寄与行為によって被相続人の財産が維持又は増加したと認められる必要がある(民法904条の2第1項)。したがって、被相続人に対する療養看護に関する寄与分が認められるためには、被相続人が自らの費用で看護人を雇わなければならない状態にあったところ、相続人が「特別の寄与」といえる療養看護を行ったことによって、被相続人が看護人に関する費用の支出を免れたと認められる必要がある。」と述べ、本件では、被相続人が自らの費用で看護人を雇わなければならない状態にあったとか、Yが「特別の寄与」に該当するような看護を行ったと認めるに足りる資料はないとして、Yの寄与分の申立てを却下した。
-
第3 抗告審決定の内容
抗告審は、令和3年1月から被相続人が入院した同年3月22日までの81日間の被相続人の病状や心身の状況、Yのした介助や介護の内容等から、特別の寄与があったと認定した。
そして、その期間中、被相続人は少なくとも要介護2相当の状態にあったものとして評価することとし、介護報酬相当額は、令和3年時点の介護保険における訪問介護の報酬基準を参考として、日額6500円とし、更に、裁量割合については、介護報酬基準は介護の資格を有する者が介護をした場合に、介護者ではなくその介護者が所属する法人等に支払われる報酬の基準であることや、被相続人は介護保険サービスをほとんど利用しておらず、子であるYが介助や介護をしていたことなどの本件に現れた一切の事情を考慮して、0.7とするのが相当であると述べた。
したがって、Yの寄与分は、6500円×81日間×0.7の計算式により算出される計算結果から1万円未満を四捨五入した37万円とするのが相当であると判示した。 -
第4 介護による寄与分の認定
1 被相続人の介護が、相続における寄与分と認められるためには、原審判が述べるとおり「特別
の寄与」(身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献)である必要がある。
そして、特別の寄与に該当するか否かは、単に「相続人がどのような介護を行ったか」という
ことだけでなく「被相続人がどのような病状にあり、どのような介護を必要としたか」が重要な
ポイントとなる。
2 実務では、被相続人の病状について、寄与分が認められるためには、「要介護度2」以上の状
態にあることが目安になるとされている。
3 また、寄与分の評価方法については、介護保険の「介護報酬基準」×日数×裁量割合とするの
が一般的であり、裁量割合は、抗告審決定のように0.7あたりが平均的な数値と言われてい
る。
4 本事案のように、被相続人が介護認定を受けていない場合には、診断書、医療カルテ、介護者
の日記等の資料から、被相続人の病状、どのような介護を必要としたかにより、要介護度を推認
することになる。