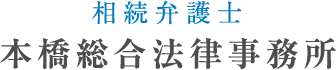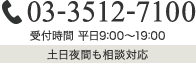![]()
死因贈与の取消が否定された事例 (東京地裁平成26年10月30日判決)
弁護士
本橋 美智子
![]()
-
第1 事案の概要(簡略化しています)
本件土地は、原告が自宅に使っていた土地であり、原告がその10分の8の持分を、原告の母が10分の2の持分(本件持分)を有していた。
平成14年に、母と原告との間で、本件持分を原告に死因贈与する契約(本件死因贈与契約)が締結された。
ところが、母は平成17年に公正証書遺言(本件遺言)を作成し、その遺言では、本件持分を含む母の財産を長女と二女(被告ら)に均等の割合で相続させると書かれていた。
母は平成21年に死亡したので、被告らは、本件遺言に基づき本件持分の移転登記をした。
そこで、原告が被告らに対し、本件持分の移転登記を求める訴訟を提起した。
この事案では、本件死因贈与契約が後に作成された本件遺言によって取り消すことができるかが争われたのです。 -
第2 本判決の内容
本判決は、死因贈与の取消の可否については、遺贈とは別個の、具体的事案に即した考察の必要があり、死因贈与の動機、態様、内容その他諸般の事情を総合して、当該死因贈与が、負担付き死因贈与と同等あるいはそれ以上に契約としての拘束力を受けるべきか、取り消されてもやむを得ないものかを具体的に判断すべきである(最高裁判所昭和58年1月24日第2小法廷判決参照)と述べた。
そして、本件死因贈与契約の目的は、母死亡時に本件持分が相続紛争の対象とならないように、原告に完全な本件土地所有権を取得させその生活基盤の安定を図るもので、原告にとって極めて重要でその期待も大きかったこと、母は、本件遺言作成時、多くの不動産の中に本件持分が含まれていることまでの意識がなかったこと等から、母による本件死因贈与契約の取消を認めず、原告の請求を認めた。 -
第3 死因贈与契約の取消の可否
死因贈与契約をその後に取り消すことができるかについては、判例、学説共に、肯定説、否定説があり、未だ確定しているとは言い難い。
本判決が引用している最高裁昭和58年1月24日判決は、訴訟上の和解で成立した死因贈与について贈与者による取消を否定したものである。
しかし、この判決は、取消が認められない例を示した事例判決であり、最高裁は死因贈与の取消については、事案ごとに取消の可否を判断していると解する説が有力である。
本判決もこの考え方に基づいているということができるであろう。