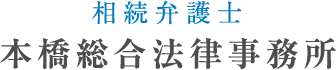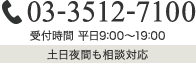![]()
同一の被相続人の相続について、再転相続人(兄弟の配偶者)として相続放棄の申述が受理された後、再転相続人(おいの母)としてした相続放棄の申述につき、申述を却下すべきことが明白であるとは認められないとして、この相続放棄を受理した事例 (東京高裁令和6年7月18日決定)
弁護士
本橋 光一郎
![]()
-
第1 事案の概要
(当事者)
被相続人Bは平成16年に死亡し、Bの法定相続人はBの兄のH一人でした。
Hは、Bの相続につき承認・放棄しないまま平成28年に死亡しました。
Hには、妻C、HC間の子であるA、同じく子(男・Bにとっては、おい)I、同じく子Dがいました。IはBの相続、Hの相続につき承認・放棄しないまま令和5年に死亡しました。Iには妻E、IE間の子F、同じく子Gがいました。なお、Iの母は前述したとおりCです。
(事実経過)
令和5年2月14日、Bの債権者Z(Bが居住していたマンションの管理組合)が、Bの法定相続人Hの相続人であるCらに対してBの相続債務の支払を請求した。
Cは、A、Dとともに、Bの相続について相続放棄の申述をし、受理された。
Cは、その(1回目の)相続放棄の際の申述書にBとの関係について「兄弟の配偶者」と記載した。
IはBの相続、Hの相続につき放棄・承認をしないまま令和5年×月○日死亡し、その後、Iの相続人たるE、F、GはBの相続について相続放棄申述をし、受理された。
Cは、その後、Iの母であり、Iの相続人の地位にあることから、その地位においてBの相続につき改めて相続放棄する必要があると考えて2回目の相続放棄の申述をした。その際、「1回目の当時は、E、F、Gが相続放棄の申述をした事実を知らなかったが、その後、その事実を知った」と主張し、(2回目の)申述書にはBとの関係について「その他(おいの母)」と記載した。 -
第2 原審(東京家裁立川支部)の判断と申述人Cによる抗告の申立
(1) 申述人(C)、A及びDは、被相続人Bの相続人亡Hの再転相続人としてBの相続につき
Hが承認・放棄するかの選択権を行使し、相続放棄の申述受理の申立てをし、いずれも受理
され、Iについても、Iの相続人であるE、F及びGにおいて、同様にHの選択権を行使
し、相続放棄の申述受理の申立てをし、いずれも受理されている。この結果、Hは初めから
Bの相続に係る相続人でなかったことになるものと解され、ひいては、申述人(C)を含む
Hの相続人らが被相続人Bの財産に属した権利又は義務を承継することもない。
(2) 申述人(C)は、本件の法律関係に照らせば、(既になされた相続放棄の申述のほかに)
重ねて相続を放棄する必要は認められないので、Cの2回目の相続放棄の申述は理由がない
から却下する。
(3) Cは、相続放棄の申述を却下した原審判に対し不服があるとして、抗告を申立てた。 -
第3 抗告審(東京高裁)の判断
(1) 抗告審は、Cの2回目の相続申述を却下した原審判を取り消して、Cの2回目の相続放棄
の申述を受理する旨の逆転決定を下した。
(2) その理由の要点は次のとおりです。
ア 相続放棄の申述は、これが受理された場合であっても、相続放棄の実体法上の効力を確
定させるものではなく、相続放棄の効力を争う者は、その旨を主張することができる一方
で、これが却下された場合には、民法938条の要件を欠くことになり、相続放棄をした
ことを主張することができなくなる。このような手続の性格に鑑みれば、家庭裁判所は、
却下すべきことが明確な場合を除いては、相続放棄の申述を受理するのが相当である。
イ 申述人(C)が、B死亡による相続について、Hの再転相続人としての地位とIの再転
相続人としての地位を併有していたと解する場合には、第1回目の相続放棄の申述は、H
の再転相続人としての地位の関係において、相続放棄をする趣旨であり、本件(第2回目
の)申述は、Iの再転相続人としての地位の関係において、相続放棄をする趣旨であると
解する見解が成り立つ余地がある。
ウ よって、本件(第2回目)申述については、却下すべきことが明白であるとは認められ
ないからこれを受理するのが相当である。 -
第4 コメント
東京高裁決定は、「相続放棄申述は、却下すべきことが明白な場合を除いて、家庭裁判所はその申述を受理するべきである」旨を判示しております。これは、いわゆる明白性基準説といわれているものであり、近時の判例通説になっているものです。東京高裁の本件決定は妥当なものと考えます。